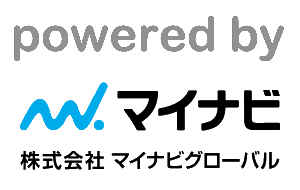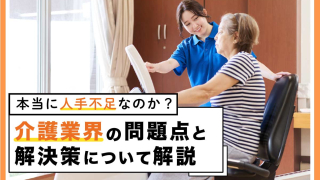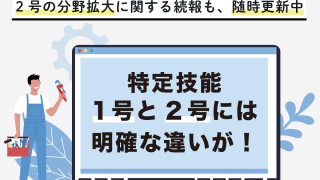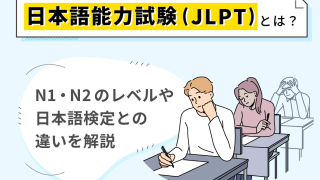【最新版】出入国管理及び難民認定法(入管法)を簡単に解説!育成就労や難民申請も紹介
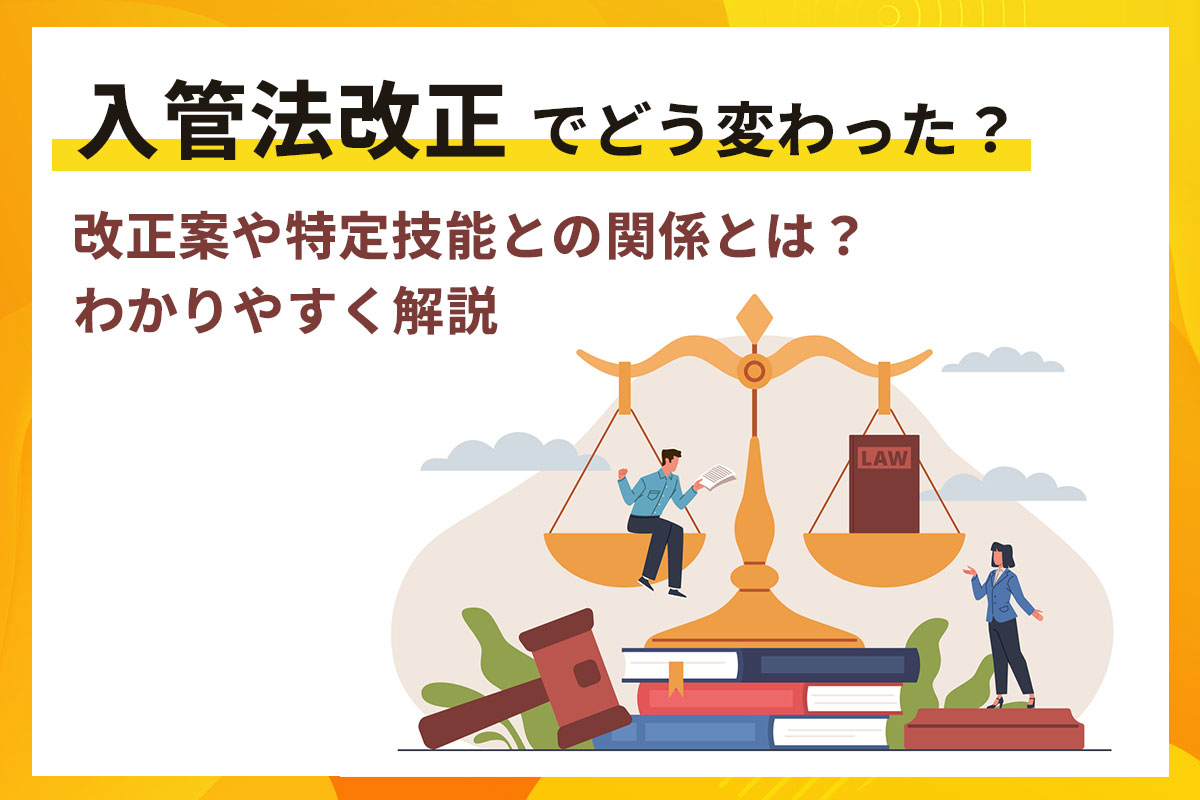
ここ数年で何度か話題となっている「入管法改正(出入国管理及び難民認定法改正)」は、外国人が日本へ入国・出国などをするにあたって避けて通れない日本の法律です。
2019年に大きな改正があった後、2021年に改正案が出たことで再び注目を浴びました。
その後、2023年と2024年に大きな改正を迎えています。2024年には育成就労制度の創設、マイナンバーカードと在留カード等の一体化に関する入管法改正がありました。
2025年4月1日には、1号特定技能外国人の支援計画に関する省令が一部改正され、特定技能受入れ機関が地域の共生施策への協力を行う責務が明確化されました。
今までの入管法からどこが変更になったのか、問題点や現在注目されている理由などに触れながら、最新の情報から過去の経緯まで行政書士がわかりやすく解説していきます。
目次
閉じる
出入国管理及び難民認定法(入管法)とは
昨今話題となっている「入管法 改正」について、どんな内容かご存知でしょうか?
そもそも入管法とは略称のことで、正確には「出入国管理及び難民認定法」といい、ポツダム命令に基づいて1951年(昭和26年)10月4日に公布されました。
その後、ボツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく外務省関係諸命令の措置に関する法律の規定により、法律として扱われるようになりました。
「出入国管理及び難民認定法」とは
内閣府男女共同参画局|出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法(入管法)は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とした法律です。
つまり入管法とは、日本への入国や出国の管理、在留資格や不法滞在、難民の認定手続きなどに関して決められた法律ということです。
すべての人が対象なので、これには外国人だけでなく、日本人も含まれます。外国人を雇用したり、受け入れる場合に必ず関係する法律といえます。
このような目的で制定された法律ですが、この数年で大きな改正が行われています。どんな点が改正されたのか、また現在改正案が審議されており、どんな案が提出されているのか、ここからは年代順にみてきましょう。
2024年の入管法改正
2024年6月14日に成立、21日に公布されたのが、「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)」「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)」です。
技能実習制度と、新たに創設される育成就労制度、2つの制度の関係する特定技能制度の3つの制度に関する入管法の改正がメインです。
2024年の改正点
・特定技能の適正化
・不法就労助長罪の厳罰化
・永住許可制度の適正化
・マイナンバーカードと在留カード等の一体化
さらに、これに合わせて「育成就労法」が作られています。
新たな在留資格「育成就労」創設
「技能実習」を廃止し、「育成就労」を創設することが決まりました。
本来の制度の創設目的と実態の不一致など、課題が多かった技能実習制度を廃止し、人材育成と人手不足解消のための人材確保の両方を目的とした在留資格です。技能実習制度の問題点と解決策、育成就労制度の内容については有識者会議における議論や提言をもとに決定されています。
育成就労制度について、詳しくは以下の記事で解説しています。
特定技能の適正化
受入れ企業(特定技能所属機関受入れ機関)が特定技能1号で在留する外国人の支援を外部委託する場合、委託先を登録支援機関に限るものとされました。これまでは一部委託の場合は登録支援機関以外にも委託が可能でした。(全支援を委託する場合は登録支援機関に限定されていた)
不法就労助長罪の厳罰化
送り出し機関などへの不法就労助長罪の罰則が厳しくなりました。
↓
拘禁刑5年以下または500万円以下 ※併科可
育成就労制度では、条件付きで「転籍」が認められることとなり、これにより技能実習で問題となっていた失踪の抑止が期待されています。
しかし、制限を緩和することで悪質なブローカーが転籍を助長する恐れが懸念されています。不法就労助長罪が厳罰化された背景には悪質な転籍ブローカーを排除する目的があります。
不法就労助長罪について詳しく知りたい場合は以下をご覧ください。
永住許可制度の適正化
永住許可制度を適正化するために、取消事由を追加しました。
具体的には「入管法上の義務違反」「故意に公租公課の支払いをしない」「特定の刑罰法令違反」の3つです。上記に該当する場合は、在留資格が取り消しになる場合があります。ただし、特段の事情がない限りは、在留資格を変更して引き続き在留を許可するそうです。
この改正は、主には税金や社会保険が未納である永住者への対策であるとされ、話題になりました。
外国人は基本的に税金を納めていない場合、在留資格を更新する際などに発覚して在留資格は取り消されます。ですから、永住者以外の外国人の方は基本的にはきちんと収めています。
しかし、永住権を持つ外国人は、永住許可後に在留審査(在留期間の更新など)がないことから、永住許可時には満たしていた納税などの義務を果たさなくなる場合が多くありました。今回の改正はこれらに対応するための措置です。
永住権の要件や取得方法は以下で詳しく解説しています。
マイナンバーカードと在留カード等の一体化
2024年6月、利便性の向上や行政運営の効率化の目的で、マイナンバーカードと在留カードの一体化に関する入管法改正がなされました。
2026年6月14日(予定)より、在留カードとマイナンバーカードがひとつになったカードが利用できるようになります。(従来どおり在留カードとマイナンバーカードを分けることも可能です。)
一体型の在留カードの場合は、企業は外国人を採用する際、マイナンバーカードの写しを保管することになります。運用開始までに情報が変更される場合がありますので、最新情報は出入国在留管理庁のページを適宜ご確認ください。
2023年の入管法改正
2023年6月9日に改正法が成立し、6月16日に公布されました。正式名称は「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律」です。
2023年の改正点は以下9点です。
- 16歳未満の外国人の在留カード等の有効期間の更新申請に関する見直し
- 補完的保護対象者の認定制度の創設
- 在留特別許可制度の適正化
- 送還停止効の例外規定の創設
- 罰則付き退去等命令制度の創設
- 自発的な帰国を促すための措置の拡大
- 監理措置制度の創設
- 仮放免の在り方の見直し
- 適切な処遇を実施するための規定の整備
この中から、特に話題となった部分をピックアップして見てみましょう。
難民認定3回目以降の申請者は強制送還を可能にする
④送還停止効の例外規定の創設
難民認定手続中の送還停止効に例外が設けられました。難民認定手続中は一律に送還が停止される現行入管法の規定(送還停止効)を改め、以下の対象者は、難民認定手続中であっても退去させることを可能になります。
- 3回目以降の難民認定申請者
- 3年以上の実刑に処された者
- テロリスト等
ただし、3回目以降の難民認定申請者でも、難民や補完的保護対象者と認定すべき「相当の理由がある資料」を提出すれば、送還は停止となります。
退去すべき外国人に自発的な帰国を促すための措置
⑥自発的な帰国を促すための措置の拡大
摘発された場合でも、自発的に帰国する場合は上陸拒否期間を短縮(5年→1年)
退去しなければならない外国人が、自ら出頭して出国命令制度により帰国をする場合、上陸拒否期間は1年に短縮されます。
改正前は出頭前に警察や入管などに摘発されてしまった場合、この出国命令制度は使うことができず、帰国をしても5年の上陸拒否期間となっていましたが、これが摘発されて帰国したとしても、1年の期間になります。
2023年の入管法改正の問題点
大きな問題点とされていた部分は、難民認定3回目以降の申請者は強制送還が可能なことです。
3回以上の申請で強制送還されてしまった場合に、保護が必要な人達を命の危険にさらしてしまう可能性が高くなります。この問題点について様々な議論がおこなわれ、結果、3回目以降の難民認定申請者でも、難民や補完的保護対象者と認定すべき「相当の理由がある資料」を提出すれば、いわば例外の例外として、送還は停止することとなりました。
また、収容の長期化・仮放免による逃亡の多発問題については、親族や知人など、本人の監督等を承諾している者を「監理人」として選び、その監理の下で、逃亡等を防止しつつ、収容せずに退去強制手続を進める「監理措置」制度が設けられることとなりました。
ただ、『難民や補完的保護対象者と認定すべき「相当の理由がある資料」を提出』する点については、審査の透明性や公平性の確保などが課題とされています。
2021年の入管法改正案は取り下げに
2021年に提出された「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案」は、その内容について課題が指摘され、採決は見送られました。
2021年入管法改正の問題点
2021年の入管法改正について人権上の問題点が多いとして、批判の声があがりました。とくに問題視されたのは以下の点です。
【問題とされた点】
◆難民認定手続き中であっても申請が3回以上の場合に強制送還を可能とする仕組み(2回申請を却下されて3度目の申請中の人)
◆強制送還を拒む行為に対する刑事罰の導入
帰国すると身に危険が及ぶおそれがあることから、難民申請を行う人については難民認定手続き中は送還を停止する「送還停止効」により、日本で生活することが認められていました。
しかし、日本の難民認定率は諸外国と比べて低い水準にとどまっているとの指摘があり、さらに入管施設に収容されていたスリランカ人女性が過酷な扱いを受けて死亡した事件をきっかけに、入管行政の在り方に対して批判や懸念が広がりました。こうした状況下で改正案の是非が大きな議論となり、最終的には採決は見送られました。
【2021年の難民認定数】
・難民認定申請者数…2,413人(前年比1,523人・約39%)減少
令和3年における難民認定者数等について|出入国在留管理庁
・難民審査請求数…4,046人(前年比1,473人・約57%)増加
・難民と認定した外国人…74人
・難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた外国人…580人
2021年改正のその後
2021年の「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案」は採決が見送られたのち廃案となりました。その後、2021年案の骨格を維持しつつ修正を加えた改正案が国会に提出され、2023年6月9日に成立、6月16日に公布されました。
2019年の入管法改正と背景
2019年4月、入管法の大きな改正が行われて、新しい在留資格「特定技能」が創設されました。改正の狙いは、日本の人口減少に伴う深刻な人手不足に対応するために、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる点にあります。
変更点:新しい在留資格「特定技能」の創設
改正により「特定技能」が創設されたことで、人手不足が深刻とされている特定産業分野は、一定の専門性・技能がある外国人を即戦力として受け入れることが可能となりました。
注目すべきは、特定技能では単純労働を含む幅広い業務が可能という点です。
それまでは身分系の在留資格以外で単純労働はできませんでしたが、特定技能の創設により、幅広い業務に従事できる道が開かれました。
また、特定技能には技能実習からの移行が可能です。技能実習生は最長で5年しか日本に在留できず、その後は必ず母国へ帰らなければなりませんでした。ところが、技能実習から特定技能への移行が可能になったことで、引き続き日本で就労できるようになりました。
特定技能については、詳しくは以下でも解説していますので、ぜひ、ご覧ください。
まとめ
本記事では、近年の入管法の改正についてご紹介しました。
外国人の受け入れに関する従来の施策の課題を解決するため、2019年から2024年にかけて新たな在留資格が創設されたり、今までの受け入れ体制について慎重な姿勢が示されたりと、多くの改正点がありました。
2019年に人手不足対策として創設された特定技能、技能実習の廃止と育成就労の創設と、人手不足や労働・雇用の問題と、外国人の受け入れ施策は密接に関係しています。育成就労制度の施行は2027年4月ですが、今後の動向に注目です。
直近2025年には、特定技能を受け入れる企業が、地域社会の取り組みに協力する責任が明確になり、自治体への「協力確認書」の提出や、共生施策への協力が必要になりました。また、定期届出の頻度も年1回に簡素化され、企業の手続きがより行いやすくなっています。
▼2026年の外国人労働者に関するニュースをまとめています