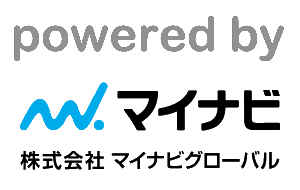【特定技能2号 農業】取得方法や試験概要、受入れの要件をわかりやすく解説

2023年6月、農業分野が特定技能2号の対象分野に追加されました。在留期間の更新回数に上限がない特定技能2号に農業分野が追加されたことにより、外国人材も農業において長期的な働き方ができるようになりました。
今回は、農業分野で特定技能2号を取得するために知っておきたい事柄について解説します。農業分野での特定技能2号の要件や技能測定試験の試験範囲、また受け入れ側の要件についても説明します。
目次
閉じる
特定技能2号とは
特定技能2号は、特定技能1号よりも熟練した技能と実務経験を積んだ外国人材が得られる在留資格です。
11の対象分野があり、農業分野では「耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)および当該業務に関する管理業務を行う」とされています。特定技能2号の対象分野で、次のような共通の特徴があります。
- 在留期間の更新上限がない
- 家族帯同が可能
- 永住権の要件を満たせる可能性がある
- 長期滞在が可能になり、キャリア計画をたてられるようになった
順に説明します。
1.在留資格の更新上限がない
特定技能2号の在留資格には、在留期間の更新回数に上限はありません。特定技能1号では通算で5年間しか在留することを許されていませんが、特定技能2号では在留期間の更新は必要であるものの、許可されれば在留し続けることが可能です。
2.家族帯同が可能
特定技能2号の外国人は、要件を満たせば配偶者と子を本国から呼び寄せることができます。呼び寄せた配偶者と子は「家族滞在」の在留資格で在留することになります。
3.永住権の要件を満たせる場合がある
特定技能2号の外国人は、日本での永住権の要件を満たせる可能性があります。永住権の申請には10年以上の在留(そのうち5年間は就労資格か居住資格での在留)が必要ですが、技能実習と特定技能1号はこの在留期間にカウントされないと決められています。特定技能2号になることで在留期間をカウントできるようになり、永住権申請の要件を満たせるため永住権取得を目指すことができます。
4.特定技能2号の外国人が長期滞在が可能になり、キャリア計画をたてられるようになった
特定技能2号は、在留期間の更新の必要はあるものの、在留期間更新回数に制限はありません。そのため日本で様々な働き方をを思い描くことが可能です。役職を持たせてマネジメント業務に就くなど、受け入れ側にとっても利益があります。
▼さらに詳しく知りたい場合は以下の記事を合わせてご覧ください。
農業分野(耕種農業・畜産農業区分)特定技能2号の概要
農業分野は「耕種農業」「畜産畜産農業」に区分されています。
従事できる仕事はこの2つに分かれ、受験できる技能測定試験も「耕種農業」と「畜産農業」に分かれています。合格した区分でのみ、働くことが許されており、例えば「耕種農業」区分に合格した方は、「畜産農業」区分で働くことはできません。
▼特定技能の農業分野全般について知りたい場合はこちらの記事をご覧ください
【在留資格申請】特定技能2号「農業」の要件
特定技能2号「農業」の在留資格申請には、下記の通り要件があります。
これらを満たすことで申請することができます。
- 2号農業技能測定試験に合格(「耕種」「畜産」に分かれる)
- 2年以上の作業工程の管理や作業員指導の経験、もしくは3年以上の現場での実務経験
技能実習の職種・作業内容と特定技能1号の業務に関連性があれば、技能実習から特定技能1号へ移行する際の試験は免除されますが、特定技能2号は試験への合格が必ず必要です。特定技能1号と大きく異なる点のため、注意しましょう。
2号農業技能測定試験の受験には、現場での経験を証明する書類が求められます。
そこで、それぞれの経験について詳細を説明します。
- 2年以上の作業工程の管理や従業員指導の経験
自らの判断で農作業(「耕種」あるいは「畜産」)を行うと共に、複数の作業員の指導や作業工程の管理を行うこと。
閑散期など指導が無い期間があっても問題はない。この場合、技能実習での経験年数には含まれない。 - 3年以上の現場での実務経験
作業工程の管理や従業員指導の経験は不問。この場合、技能実習での経験も含まれる。
※①、②のどちらも日本以外の国での経験を含むことも可能だが、実務経験証明書を日本語で記載してもらう必要がある。
上記で注意したい点は、「耕種」で経験を積んでも、「畜産」の技能測定試験を受験することはできないことです。また、逆も同様です。
他分野と違うのは「3年以上の現場の実務経験」で要件を満たせる点です。他分野は管理・指導経験2年程度を要件とすることが多いのですが、農業分野は現場での実務経験のみでも特定技能2号が目指せます。
受け入れ側(雇用主や事業者)の要件
特定技能2号「農業」の外国人材を受け入れる側にも要件があります。
- 耕種農業もしくは畜産農業を営んでいる
- 労働者を一定期間以上雇用した経験がある※
- 雇用契約を結んでいるか
- 農業特定技能協議会の構成員になり、求めに応じて協力をする
※過去5年以内に技能実習生を含んだ同一の労働者を、少なくとも6カ月以上継続して雇用した経験、またはこれに準ずる経験(過去5年以内に6か月以上継続して労務管理に関 する業務に従事した経験)。
派遣先になる場合は、派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とすること。
ちなみに、特定技能1号のように、受け入れる外国人への支援は、義務づけられていません。
特定技能協議会について
特定技能協議会は、特定技能の制度や情報の周知、法令遵守の啓発などをおこなっています。農業分野は「農業特定技能協議会」に加入する必要があります。
協議会に関する詳細は以下をご覧ください。
特定技能2号「農業」の在留資格申請の流れ
特定技能2号の在留資格申請の流れは、以下の①~③の流れが基本となっています。
- 特定技能1号の外国人材に2年以上の工程管理や作業指導の実務経験、もしくは3年以上の作業経験を積む
- 2号農業技能測定試験の受験、合格(受験の際に①の経験を証明する書類が必要)
- 在留資格変更許可申請書など、特定技能2号の申請に必要な各種書類を用意し、最寄りの出入国在留管理局・支局(空港支局を除く)に提出する
農業分野の特定技能2号測定試験について
先ほど要件について説明した通り、特定技能2号の在留資格申請のためには、2号農業技能測定試験を受験し合格しなければなりません。
詳しく解説をします。
試験範囲
2号農業技能測定試験の試験範囲は、耕種農業もしくは畜産農業と、安全衛生管理です。学科試験と実技試験で構成されています。
■ 耕種農業全般 (マネジメント能力含む)
| 学科試験 | 実技試験 (イラストや写真による判断) |
|---|---|
| 耕種農業一般 | 肥料・農薬の取り扱い |
| 栽培作物の品種・特徴 | 種子の取り扱い |
| 栽培環境(施設・設備等) | 環境管理、資材・送致・機械の取り扱い |
| 栽培方法・管理 | 栽培に関する作業 |
■ 畜産農業全般 (マネジメント能力含む)
| 実技学科試験 | 実技試験 (イラストや写真による判断) |
|---|---|
| 肥料・農薬の取り扱い | 個体の取り扱い |
| 種子の取り扱い | 個体の観察 |
| 環境管理、資材・送致・機械の取り扱い | 飼養管理と器具の取り扱い |
| 栽培に関する作業 | 繁殖・生理 |
| 病害虫 |
特定技能2号外国人が携わっているのが耕種か畜産なのかで分かれますが、安全衛生管理はどちらの分野でも共通して出題されます。
試験の申し込み方法
2号農業技能測定試験の申し込みは、以下の手順で行います。
- 受験要件を満たしているかチェック…「2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書」、「誓約書」を全国農業会議所にWEB上で提出
- アプリケーションナンバーの発行…全国農業会議所が①の内容を確認次第発行
- 予約受付サイトより申し込み…専用の予約受付サイトより申し込み
①~③の流れで、2号農業技能測定の予約を行います。
①で記載した通り、受験には「2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書」を全国農業会議所に提出する必要があります。書類の確認には7~10日間程度かかるので、余裕をもった提出を心掛けましょう。
また、予約受付サイトの申し込み期限は4営業日前です。こちらも余裕をもって予約しましょう。
試験の費用
2号農業技能測定試験の受験料は、15,000円です。
予約完了後、試験のキャンセルはできません。予約受付期限後の変更は基本的にはできず、予約内容に誤りがあった場合でも予約完了後は修正やキャンセルはできません。基本的に、予約を完了したら変更はできないと考えていいでしょう。試験当日に出席・欠席に関わらず受験料金が返金されることはないので、気を付けてください。
試験方式と試験結果の確認方法
試験はCBT方式で行われます。また、試験結果は試験終了後すぐにパソコン画面に表示されます。
結果通知書は受験後5営業日以内に自分のパソコンからマイページに入り確認可能です、。この結果通知書が、特定技能2号の在留資格申請に必要な「合格証明書」となります。印刷しておきましょう。
試験結果のデータ・スコアレポートはは全国農業会議所で5年間は保存されます。試験結果データの保存期間中は、専用ウェブサイトから随時入手可能です。
試験の合格基準と合格率
2号農業技能測定試験の合格基準は、総合得点が全国農業会議所の定める判定基準点を超えている程度です。日本での実務経験が7年以上あれば、3割程度が合格する程度とされています。
2024年9月の試験結果の受験者数と合格者数は、以下の通りです。
| 試験区分 | 受験者数(人) | 合格者数(人) |
|---|---|---|
| 耕種農業全般 | 345 | 107 |
| 畜産農業全般 | 84 | 48 |
| 合計 | 429 | 155 |
合格率は耕種で3割程度、畜産で5割程度となっています。
試験問題参考:学習用テキスト
試験問題は公表されていませんが、学習用テキストが公開されています。学習用テキストから試験のおおまかな内容を推測できます。
耕種農業区分
耕種農業区分の学習用テキストの一部を抜粋します。
①稲作
稲作とは、イネの栽培のことです。イネにはアジアを中心に世界で栽培されているアジアイネと西アフリカを中心に栽培されているアフリカイネがあります。……(続く)。
②野菜
2021年の野菜産出額は約2兆1千億円で、農業生産額の約24%です。……(続く)。
学習用テキストでは、日本の農業の基礎的な知識だけでなく、植物の構造や農作業用語まで記載されています。
畜産農業区分
畜産農業区分の学習用テキストの一部抜粋します。
①日本の農業の現状
日本の農業従業者は減少傾向で推移しており、各地で高齢化が進んでいます。そのため農業の生産条件が不利な中山間地域を中心に、作付けが行われなくなり、耕作放棄地が年々増加しています。……(続く)。
②畜産
日本の家畜は、おもに牛、豚、鶏の3つです。
牛には、肉にする肉用牛と乳をしぼる乳用牛があります。……(続く)。
畜産農業区分の学習用テキストも、日本の畜産の基礎的なことをはじめとした、畜産の具体的な作業内容まで記載されています。
2区分共通:安全衛生管理
2号農業技能測定試験には、耕種農業区分と畜産農業区分のどちらを選んでも、安全衛生管理が出題されます。こちらも学習用テキストが公開されており、このテキストで勉強することができます。
安全衛生管理の学習用テキストも一部を抜粋します。
①労務管理
労務管理は、労働者の仕事に対する意欲を失わせたり、損なわないようにするために行う、労働者に関する施策のことです。……(続く)。
②労働基準法とは
賃金は原則として、働いた労働時間分が支払われます。時給制であれば、その賃金額は働いた労働時間の分ですし、月給制の場合、その月額賃金の額は、「月の所定労働時間と労働した場合の賃金」となります。……(続く)。
以上の抜粋で、まず安全衛生管理区分では労務管理の知識が求められていることがわかります。他にも、農薬や肥料の取り扱い、廃棄物の分け方など、幅広い知識が求められることが学習用テキストから読み取れます。
試験と日本語能力の関連性
2号農業技能測定試験と日本語能力は、深い関係があるといえます。試験参加者によると、試験問題にはルビがついているそうです。他分野の試験ではルビなしの場合も少なくはないため、その意味では日本語読解力は他分野より易しいと予想されます。
基準となる日本語能力レベルは、JLPT(日本語能力試験)のだいたいN3レベル以上は必要と考えてください。N2程度あると安心ではないかと思います。
N3レベルの基準は、以下の通りです。
■N3レベルは、日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる。
【読む】
- 日常的な話題について書かれた具体的な内容を表す文章を、読んで理解することができる
- 新聞の見出しから情報の概要をつかむことができる
- 日常的な場面で目にする難易度がやや高い文章は、言い換え表現が与えられれば、要旨を理解することができる
【聞く】
- 日常的な場面で、やや自然に近いスピードのまとまりのある会話を聞いて、話の具体的な内容を登場人物の関係などとあわせてほぼ理解できる
特定技能「農業」2号の注意点
特定技能「農業」2号の取得における注意点は、管理指導や現場の実務経験の条件を技能測定試験までに満たさなければいけない点です。
管理指導の経験だけではなく、現場の実務経験のみでも農業分野では特定技能2号を取得できるようになっていますが、それでも3年以上の実務経験が必要です。
特定技能1号として、別の分野から転職してきた場合は間に合わない可能性があります。同じ農業分野で転職した場合は、前職場から、実務経験証明書を貰いましょう。連絡をしても実務経験証明書を以前の職場から発行してもらえない場合は、農林水産省へ問い合わせてください。
逆に、退職者から実務経験証明書の発行依頼連絡を受けた場合は、企業は基本的に発行をしてあげましょう。
まとめ
農業分野における特定技能2号は、「耕種農業」と「畜産農業」に分かれています。農業分野とひとくくりにされていますが、この点については注意しましょう。
特定技能2号は永住権を目指せる在留資格なので、永住を望む外国人材にとっては魅力的です。しかし、特定技能2号として認められるには、2号技能測定試験に合格する必要があります。農業分野においても、外国人材にとってはこれがひとつのハードルとなりますが、学習用テキストが用意されてあるので、事前に農業分野の知識とあわせて日本語をしっかりと学習すれば試験に合格できるでしょう。合格率も低い数字ではありません。
特定技能2号の受け入れ側は事前の準備・情報を集めて、計画的に特定技能2号の取得をサポートしていくことをおすすめします。