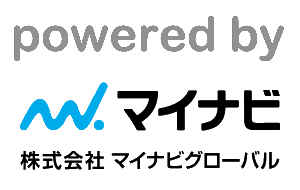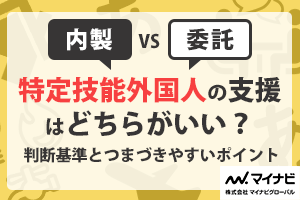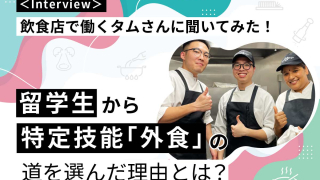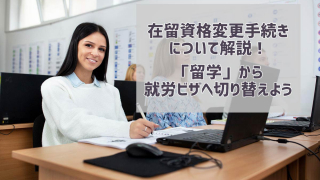特定技能「工業製品製造業」分野とは?製造業の対象業種・要件や採用の注意点を解説!

2019年4月、日本政府は人材不足に悩む分野において、外国人を対象に新たな在留資格である「特定技能」を設けました。
少子高齢化により深刻化する労働力不足を解消するため、一定の技能と専門性を持った外国人を即戦力として雇用する制度です。
今回は、特定技能「工業製品製造業」分野について、特定技能外国人を採用する方法や要件などを解説します。
目次
閉じる
工業製品製造業分野(製造業)とは?
日本では少子高齢化の影響もあり、中小企業・小規模事業者をはじめとした人手不足が深刻化しています。特に日本の製造業は長年にわたり人材不足に直面しているため、必要な技能を持つ外国人労働者を受け入れる取り組みが進められています。
在留資格「特定技能」は2019年4月に『人材の確保が困難な状況にある産業上の分野を対象に、一定の専門性・技能を持ち、現場で即戦力となる外国人を受け入れていく』ために創設されました。
複数ある分野の中でも、製造業で働ける特定技能の分野は「工業製品製造業」と呼ばれています。
製造分野の特定技能で働く外国人労働者は非常に多い
製造分野で働いている特定技能外国人は現在45,183人(2024年12月末時点)と特定技能の対象業種の中でも比較的大きなセクターであり、製造分野は大きな割合を占めていると言えます。
また、出入国在留管理庁が公表している今後5年間での受け入れ見込数は173,300人で、特定技能の産業分野の中では一番受け入れ見込数が多い分野となっています。
3分野が統合し「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」、更に「工業製品製造分野」に名称変更
特定技能の製造分野はもともと「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」という3つの分野に分かれていましたが、「産業機械製造業」での受け入れ人数が上限を超え新規入国が止まってしまったため2022年5月に統合され「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」となりました。
さらにその後、名称は「工業製品製造業」へ変更となり、新たな業種・業務区分が追加されました。
ここからは、「製造業」と省略して記載します。
製造業の特定技能外国人採用や、雇用後の支援についてのご相談ならマイナビグローバルへ。
「製造業」で受け入れ可能な業種・業務区分
分野名を「工業製品製造業」に変更後、製造分野は全10区分となりました。対象となる区分は以下の通りです。
- 機械金属加工区分
- 電気・電子機器組立て区分
- 金属表面処理区分
- 紙器・段ボール箱製造区分
- コンクリート製品製造区分
- RPF製造区分
- 陶磁器製品製造区分
- 印刷・製本区分
- 紡織製品製造区分
- 縫製区分
各区分の内容と技能について細かく見ていきましょう。
機械金属加工区分
機械金属加工区分は金属やプラスチックなどの素材に熱や圧力を加えて、形を作った部品や部材を製造する区分です。
機械金属加工区分に含まれる技能
- 鋳造機械加工
- ダイカスト
- 金属プレス加工
- 鉄工仕上げ
- 工場板金機械検査
- 機械保全電気機器組立て
- プラスチック成形
- 塗装
- 溶接
- 工業包装
- 金属熱処理 NEW!
- 強化プラスチック成形 NEW!
電気・電子機器組立て区分
電気・電子機器組立て区分とは、工場や事務所内で使用される機械を製造する区分です。工作機械などを用いて素材の加工や、機械の組み立てなどを行います。主に建設機械、農業機械、工業機械、木工機械など、あらゆる産業において必要とされる機械を製造します。
電気・電子機器組立て区分に含まれる技能
- 機械加工
- 仕上げ
- 機械検査
- 機械保全
- 電気機器組立て
- 電子機器組立て
- プラスチック成形
- プリント配線板製造
- 工業包装
- 強化プラスチック成形 NEW!
金属表面処理区分
金属表面処理区分とは、強度や耐久性を高めるため金属製品の表面を処理することで金属の強度や耐久性を高める区分です。
金属表面処理区分に含まれる技能
- めっき
- アルミニウム陽極酸化処理
追加された7つの業務区分と含まれる技能
以下は新たに追加となった7区分と、その区分に含まれる技能です。
- 紙器・段ボール箱製造業区分
- 紙器・段ボール箱製造
- コンクリート製品製造業区分
- コンクリート製品製造
- RPF製造業区分
- RPF製造
- 陶磁器製品製造業区分
- 陶磁器工業製品製造
- 印刷・製本区分
- 印刷
- 製本
- 紡織製品製造区分
- 紡績運転
- 織布運転
- 染色
- ニット製品製造
- たて編ニット生地製造
- カーペット製造
- 縫製区分
- 婦人子供服製造
- 紳士服製造
- 下着類製造
- 寝具製作
- 帆布製品製造
- 布はく縫製
- 座席シート縫製
関連業務はメイン業務に付随的する形で認められる
工業製品製造業の仕事に関わるうえで、関連して一緒に行われる作業については、付随的に行うことが認められています。たとえば、原材料や部品の調達・運搬、前後の工程の作業、クレーンやフォークリフトの操作、清掃や設備の保守管理などが含まれます。ただし、これらの関連業務だけを行うことは認められていません。
受け入れ企業の要件
特定技能外国人を雇用するには、受け入れる企業の産業が日本標準産業分類のうち以下のいずれかに該当している必要があります。
- 製造分野で特定技能1号のみ受け入れ可能な事業所の日本標準産業分類
- 11:繊維工業
- 141:パルプ製造業
- 1421:洋紙製造業
- 1422:板紙製造業
- 1423:機械すき和紙製造業
- 1431:塗工紙製造業(印刷用紙を除く)
- 1432:段ボール製造業
- 144:紙製品製造業
- 145:紙製容器製造業
- 149:その他のパルプ・紙・紙加工品製造業
- 15:印刷・同関連業
- 18:プラスチック製品製造業
- 2123:コンクリート製品製造業
- 2142:食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業
- 2143:陶磁器製置物製造業
- 2211:高炉による製鉄業
- 2212:高炉によらない製鉄業
- 2221:製鋼・製鋼圧延業
- 2231:熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
- 2232:冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
- 2234:鋼管製造業
- 3299:他に分類されないその他の製造業(ただし、RPF製造業に限る。)
- 484:こん包業
- 2299:他に分類されない鉄鋼業(ただし、鉄粉製造業に限る。)
- 2441:鉄骨製造業
- 2443:金属製サッシ・ドア製造業
- 2446:製缶板金業(ただし、高圧ガス用溶接容器・バルク貯槽製造業に限る。)
- 2461:金属製品塗装業
- 2499:他に分類されない金属製品製造業(ただし、ドラム缶更生業に限る。)
- 2291:鉄鋼シャースリット業
- 製造分野で特定技能1号・2号どちらも受け入れ可能な事業所の日本標準産業分類
- 2194:鋳型製造業(中子を含む)
- 225:鉄素形材製造業
- 235:非鉄金属素形材製造業
- 2422:機械刃物製造業
- 2424:作業工具製造業
- 2431:配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
- 245:金属素形材製品製造業
- 2462:溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
- 2464:電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
- 2465:金属熱処理業
- 2469:その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)
- 248:ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
- 25:はん用機械器具製造業(ただし、2591消火器具・消火装置製造業を除く。)
- 26:生産用機械器具製造業
- 27:業務用機械器具製造業(ただし、274医療用機械器具・医療用品製造業及び276武器製造業を除く。)
- 28:電子部品・デバイス・電子回路製造業
- 29:電気機械器具製造業(ただし、2922内燃機関電装品製造業を除く。)
- 30:情報通信機械器具製造業
- 3295:工業用模型製造業
上記の産業に該当しているかは、特定技能1号の外国人が従事する事業所において、直近1年間で製造品出荷額などが発生しているかどうかで判断されます。
事業者所有の原材料で製造している
もう一つの要件として、売り上げを得た製造品は事業所が所有する原材料によって製造され、出荷されている必要があります。
製造出荷に該当する例
次のケースも製造品出荷に含まれます。
- 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの
- 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)
- 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み,直近1年間中に返品されたものを除く)
協議会に加入(在留資格申請前)
企業が特定技能外国人を受け入れるためには、経済産業省が設置する「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」への加入が必要です。
加入のタイミングは、在留資格申請前と定められており、手続きは「特定技能外国人材制度(製造3分野)ポータルサイト」内の「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」ページにある「特定技能外国人を雇用したい企業の方はこちら」から行うことができます。
注意点として申請から入会完了までは通常2カ月程度かかるとされており、多くの事業所では1~2回の修正対応が求められるため、在留資格申請に間に合うよう余裕をもって手続きを進める必要があります。なお、入会が完了するのは、受入れ協議・連絡会の構成員名簿に掲載された時点となります。
「紡織製品製造」「縫製」は追加要件あり
「紡織製品製造」「縫製」の技能実習制度において時間外労働に対する賃金不払等の違反が多いことから、違反をなくし適正な取り引きを推進するため、下記の追加要件が設定されています。
- 国際的な人権基準を順守し事業を行っていること
- 勤怠管理を電子化していること
- パートナーシップ構築宣言の実施
- 特定技能外国人の給与を月給制とする
①国際的な人権基準を順守し事業を行っていること
企業は、「国際的な人権に関するルールを守って事業を行っていること」が求められます。具体的には、外部の監査機関による審査を受け、その内容が公開されている基準にきちんと合っていることが必要です。
対象となる監査・認証例
- GOTS
- OEKO-TEX STeP
- Bluesign
- Global Recycled Standard (GRS)
- 日本アパレルソーイング工業組合連合会-取引行動規範ガイドライン(JASTI)
※今後、認証制度が追加される可能性があります。
審査事項
- 対象となる監査・認証のいずれかを取得していること
- 特定技能外国人を受け入れるための申請時点で認証の有効期限が3カ月以上残っていること(認証は年監査レポートの日付から有効期限があります。有効期限は監査機関によって異なります。)
- 受入れ事業所単位で監査・認証を取得していること
特定技能外国人を受け入れるためには、上記内容を示す監査・認証のレポートや、認定証の提出が必要です。そのために、第三者の認証機関や監査機関による審査を受ける場合は、下記の考え方を基に設定された全84項目に上る監査要求事項項目案を満たしているかどうかを判断されます。
監査要求事項項目案を一部抜粋
- 強制労働の廃止
身体的または心理的暴力の使用を禁止するポリシーの基準の制定 - 児童労働の撤廃
児童労働法令遵守方針の基準の制定 - 差別・ハラスメントの禁止
性別に基づく差別の禁止に特化して関連する基準の制定 - 結社の自由・団体交渉権
結社の自由と団体交渉が法律で制限されている国における労働者代表の形成に関する基準の制定 - 労働安全衛生
職場の安全に関する基準の制定 - 福利厚生
雇用条件の伝達基準の制定 - 賃金
公正かつ適時な賃金支払いに関する基準の制定 - デューディリジェンス
人権に関する方針・手続きの基準の制定 - 外国人労働者(技能実習生を含む)関連
安全手順が現地の言語で書かれている/労働者が理解できるかどうかの基準
監査要求事項項目案の詳細を確認したい場合は経済産業省のHPをご覧ください
▶参考:繊維(METI/経済産業省)
②勤怠管理を電子化していること
『勤怠管理の電子化要件 登録システム一覧』に掲載されたシステム、または同等の要件を満たす自社開発システム等を導入し、受入れ事業所で実際に活用していることが求められます。
また、審査時には登録システムを導入していることを示す資料や実際の活用状況がわかる写真の提出が求められます。
登録システム以外を使用する際に必要な要件
- 電子的に出退勤を記録できること(例:ICカード、指紋認証、顔認証、タブレットタップ)
- 手作業を介さずデータ送信ができること(※紙からPCへの転記やエクセル編集できるCSV形式は不可)
- タイムカード使用時もデータ送信対応が必要
- 打刻時間の修正は原則本人が行い、管理者修正時は本人同意が必要
- 打刻時間の実績と修正後の記録の両方を確認できること
勤怠管理のIT化は、適切な労務管理を実現するとともに、労務業務の効率化や生産性向上を促進し、特に中小企業や小規模事業者においては、リアルタイムでの出退勤データの把握や、不正打刻の防止、労働時間を可視化することで管理部門の負担軽減や経営者自身の働き方改革にも貢献するため、これを機に勤怠管理を整えていきましょう。
③パートナーシップ構築宣言の実施
パートナーシップ構築宣言とは、企業が取引先との共存共栄を目指して取り組む内容を「代表権のある者の名前」で宣言し、専用ポータルサイト上で公表する制度です。
主な取り組み内容
- 原材料の調達から販売までの流れ、いわゆるサプライチェーン全体の価値や利益を増大させるために、より良い商品やサービスになるように工夫した取り組みと新たな連携(例:IT導入、BCP策定、グリーン調達支援など)
- 下請企業との望ましい取引慣行の遵守(価格決定方法の適正化、型管理の適正化、現金払い原則の徹底、知財・ノウハウの保護、働き方改革に伴う「しわ寄せ」防止)
受入れ機関に求められる追加要件は企業単位で「パートナーシップ構築宣言」を行っていることです。そのため、事業所単位での宣言は不要ですが、下記資料の提出が求められます。
- 「パートナーシップ構築宣言」のポータルサイト上で自社が掲載されている箇所を赤枠で示したスクリーンショット
- 自社のホームページに掲載されている宣言文のPDF
- 「パートナーシップ構築宣言」のポータルサイトで、自社の名前が掲載されているページのURLの提示
④特定技能外国人の給与を月給制とする
季節や受注量による仕事量の変動で、外国人労働者の生活が不安定にならないよう、安定的に給与を支払う「月給制」を採用することが求められます。
月給制の要件
- 会社都合の休業や有給休暇取得を欠勤扱いして基本給から控除するのは禁止
- 有給休暇を全て消化後や、本人が取得を希望しない欠勤は基本給から控除可能
- 労働日数や時間が変動しても、「月単位で算定した額」で給与を支給する必要がある
- 他の日本人職員が日給制でも、特定技能外国人は必ず月給制を適用する
審査の際には規定様式の誓約書を受け入れ企業の代表者名で提出する必要あります。
製造分野の特定技能1号の取得の要件
外国人が特定技能「製造業」の在留資格を取得する方法は2つあります。ひとつは、特定技能1号評価試験および日本語評価試験に合格することで、もうひとつは技能実習2号から移行することです。
特定技能1号の取得方法
- 試験に合格する(技能評価試験・日本語試験)
- 技能実習2号(育成就労)からの移行
①試験に合格する
技能評価試験である「製造分野特定技能1号評価試験」と、日本語試験(日本語能力試験のN4以上もしくは、国際交流基金日本語基礎テスト)に合格する必要があります。
- 「製造分野特定技能1号評価試験」に合格
- 日本語試験(日本語能力試験(JLPT)のN4以上、もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic))に合格
技能評価試験に合格する
特定技能1号評価試験は、学科と実技の両方で構成されており、国内外の試験会場で受けることができます。試験は業務区分ごとに異なり、従事したい業務の区分の試験を受験します。
特定技能1号評価試験についてさらに詳しく知りたい方はこちら
日本語試験に合格する
日本語能力試験(JLPT)のN4レベルの合格が必要です。レベルはN1からN5までの5つのレベルがあり、もっとも難易度が高いのはN1でもっとも簡単に合格できるのはN5です。試験は通常、年2回実施されます。
N1認定の目安は「幅広い場面で使われる日本語を理解することができる」こと、N5認定の目安は「基本的な日本語をある程度理解することができる」ことです。では特定技能に求められる日本語レベルのN4の目安はというと、「基本的な日本語を理解することができる」とされています。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)は日本語能力試験(JLPT)と異なり、試験は1種類のため、得点に応じて日本語レベルを判断されます。特定技能として就労資格を得るためには、試験で250点満点中200点以上を取得し、A2以上の日本語能力があると認められる必要があります。国内の試験会場によっては連日のように試験が開催されていますので、受験のチャンスが多くあります。
試験の詳しい開催日程などの情報は、以下から確認できます。参考にご覧ください。
▶開催日程|国際交流基金日本語基礎テスト
②技能実習2号からの移行
「工業製品製造業分野」に該当する職種において技能実習2号を修了している外国人は、技能評価試験および日本語試験を受験することなく特定技能1号へ移行することができます。
ただし、技能実習2号から特定技能1号に移行できる職種は決まっていますのでご注意ください。詳細に関しては厚生労働省のHPをご確認ください。
▶参考:技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(PDF)|厚生労働省
製造分野の特定技能2号の取得の要件
特定技能2号は2023年に対象分野が拡大し、製造分野も対象となりました。特定技能2号の申請要件には特定技能1号での実務経験や試験合格も必要です。
【特定技能2号申請要件】
- 取得方法①:特定技能2号評価試験ルートの場合の要件
- 「製造分野特定技能2号評価試験」合格
(生産管理プランニング区分、生産管理オペレーション区分のいずれか) - 「ビジネス・キャリア検定3級」の取得
(機械金属加工区分、電気電子機器組立て区分、金属表面処理区分のいずれか) - 日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験
- 「製造分野特定技能2号評価試験」合格
- 取得方法②:技能検定ルートの場合の要件
- 技能検定1級の取得
(鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、工業包装のいずれか) - 日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験
- 技能検定1級の取得
特定技能2号評価試験
特定技能2号評価試験は学科試験・実技試験両方の合格が必要です。
特定技能2号を取得するためには、特定技能2号評価試験への合格は必須ですが日本語試験への合格は必要とされていません。2号評価試験やビジネス・キャリア検定で、それに相当する日本語能力があるかどうかは確認できるものと考えられているため、2号評価試験の受験者は一定程度の日本語能力がある方を想定しています。
特定技能評価試験について
特定技能評価試験について詳細を解説します。
特定技能1号評価試験
| 試験区分 | 全10区分 |
| 試験場所・試験日程 | 最新の試験場所および試験日程はポータルサイトより確認 |
| 試験時間 | 学科試験・実技試験あわせて80分 |
| 実施方式 | CBT(コンピューター・ベースド・テスティング)方式(学科、実技) |
| 言語 | 日本語 |
| 試験水準 | 特定技能1号の試験免除となる技能実習2号修了者が受験する技能検定3級試験程度を基準 |
| 合否の基準 | ◼学科試験:正答率65%以上 ◼実技試験:正答率60%以上 |
試験会場や日程については下記サイトより確認できます。
▶参考:製造分野特定技能1号評価試験-試験案内|特定技能外国人材制度(製造3分野)
特定技能2号評価試験
| 試験区分 | 全3区分 |
| 試験場所・試験日程 | 最新の試験場所及び試験日程はポータルサイトより確認 |
| 試験時間 | 実技試験のみ80分 |
| 実施方式 | CBT(コンピューター・ベースド・テスティング)方式 (実際の作業工程や材料に関連する内容を選んで、正しい答えを選ぶ) |
| 言語 | 日本語 |
| 試験水準 | 2号特定技能外国人が現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等、またはそれ以上の高い専門性・技能を要することを踏まえ、技能検定1級程度を基準とする |
| 合否の基準 | 正答率65%以上 |
試験会場や日程については下記サイトより確認できます。
▶参考:製造分野特定技能2号評価試験-試験概要
実務経験が求められる
製造分野特定技能2号評価試験を受験するには、試験の前日までに日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験が必要です。また、申し込み時には実務経験証明書の事前提出が求められます。
特定技能2号評価試験の申し込み方法に注意
特定技能2号評価試験の申し込みには実務経験証明書が必要となりますが、2024年度より、実務経験証明書の申請方法が変更となりました。
申請の流れは以下の通りです。
1.実務経験証明書を作成する
特定技能2号評価試験の受験者は、実務経験証明書の作成が必要です。そのため、雇用している外国人から実務経験証明書の記入を依頼された場合は、記載に協力しましょう。
提出方法などの詳細については下記サイトより確認できます。
▶参考:実務経験証明書|製造分野特定技能評価試験|特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)ポータルサイト
2.専用フォームから申請する
経済産業省のポータルサイトにある「受験資格確認番号の取得申請(実務経験証明書の提出)」フォームより、受験者資格確認番号を申請してください。
専用フォーム:https://cbt.sswm.go.jp/mail
3.事務局にて書類確認
事務局にて、申請内容を確認します。(不備がある場合は、メールに記載された内容を修正のうえ、メールに記載の申請フォームから再登録してください。)
4.メールにて、受験者の受験資格確認番号を受け取る
実務経験証明書に問題がない場合、受験者専用の「受験資格確認番号」がメールで送付されます。
※不備がある場合、予約したい時期までに番号が受け取れない場合があります。書類は十分確認し、余裕をもって申請しましょう。
5.プロメトリックの予約時に、自身の「受験資格確認番号」を入力
プロメトリックの予約画面で、受験者の受験資格確認番号を入力して下さい。(事務局に申請した情報や受験資格確認番号が一致しない場合は、予約することができません。)
特定技能2号評価試験問題サンプル
作業を安全に行うための整理・整頓として間違っているものを、選択肢A~Dの中から一つ選びなさい。
<選択肢>
A.作業場所、通路、製品や材料置き場を区分する。
B.材料の入れ替えが大変なので、通路も使用し多くの材料を作業場所に保管しておく。C.作業の工程や流れに合わせて作業台や設備を配置する。
D.異常時の避難や設備・作業台とのぶつかりがないよう適切な作業スペ-スを確保する。
<解答と解説>
解答:B
✓製造業の現場において、「5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)」は重要であり、常に心がけておく。
✓転倒の原因にもなるため、通路に材料を置いてはいけない
採用で注意すべきこと
特定技能協議会へ加入できない場合があります。
加入不可となる主な理由は、特定技能外国人を雇用しようとする企業や個人事業主が特定技能制度の条件を満たしていない場合です。
製造業分野は、条件が複雑であり、例えばドアノブを製造する事業所は特定技能外国人が従事できる産業分類には該当しないので、申請後に加入が認められないという事例があります。
協議会への加入が不可能な場合、その企業や事業主は特定技能外国人を雇用することができませんので、加入申請前に特定技能制度の条件を正確に理解し、準備を整えることが大切です。
まとめ
今後、人材不足と高齢化が進む製造業では、特定技能の外国人材に課される期待がますます高くなると予想されます。
特定技能外国人を採用するには、法令に定められた要件を満たすとともに、外国人材への支援などを適正に実施しなければなりません。
外部のサービスを上手に活用しながら、特定技能外国人の採用を考えてはいかがでしょうか。