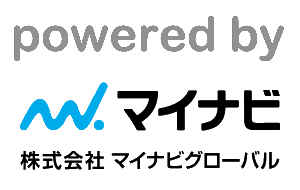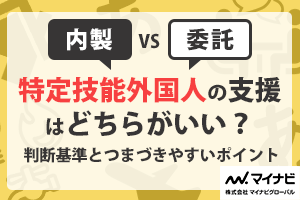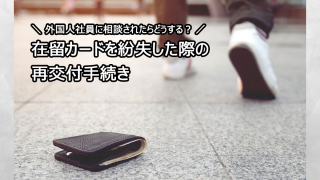特定技能「介護」とは?受入れ要件や技能実習との違い、メリットを解説

特定技能「介護」は、介護職に就くことができる在留資格のうちの一つです。介護職に就ける在留資格として、「介護」、「EPA」、「技能実習」、特定技能「介護」の4つがあります。「介護」以外は介護福祉士の資格がなくても介護の仕事に従事できます。
そのなかでも、介護職として働いてほしい場合におすすめの特定技能「介護」は、他の在留資格と比較してどのような特徴があるのでしょうか?
今回は、特定技能「介護」について、対応可能な仕事内容や、試験の概要などについてご説明します。
目次
閉じる
特定技能「介護」とは
「特定技能」は深刻化する人手不足を解消するため、2019年に創設した制度および在留資格です。
現在、対象となる分野は16分野あり、「介護」はそのうちのひとつです。
- 特定技能「介護」で従事可能な業務
- 身体介護など(介護を受ける人の状況にあわせて入浴、食事、排せつを助けること等)
- 身体介護などに関係して助けが必要な仕事(レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助等)
特定技能「介護」の在留期間は通算5年です。5年を超えて日本で働きたい場合、特定技能1号から介護福祉士の資格を取得し、在留資格「介護」で在留することになります。
在留資格「介護」の取得方法や詳細については以下の記事をご覧ください。
▶在留資格「介護」(介護ビザ)とは?他在留資格との違いや雇用方法などを解説
▶外国人が介護福祉士資格を取得する方法|合格率や企業ができるサポートも解説!
訪問介護などの訪問系サービスへの従事が可能に!
2025年4月より、訪問系サービスも特定技能の対象となりました。具体的には、訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、訪問型サービス(総合事業)などです。
特定技能「介護」の場合は、通常の特定技能「介護」の要件に加えて、以下の要件を満たすことで訪問介護などの訪問系サービスの業務に従事することが可能です。
- 訪問系サービスの要件
- 介護職員初任者研修課程などを修了
- 介護事業所などでの実務経験等(※)を有する特定技能外国人
※ 介護事業所等での実務経験が1年以上あることを原則とする
さらに、受入れ事業所は、利用者・家族へ事前に説明を行うとともに、以下の事項を遵守する必要があります。
- 遵守事項
- 外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項などに関する研修を行うこと
- 外国人介護人材が訪問介護などの業務に従事する際、一定期間、責任者などが同行するなどにより必要な訓練を行うこと
- 外国人介護人材に対し、訪問介護などにおける業務の内容などについて丁寧に説明を行いその意向などを確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること
- ハラスメント防止のために相談窓口の設置などの必要な措置を講ずること
- 外国人介護人材が訪問介護などの業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合などに適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと
▶参考:外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について|厚生労働省
訪問系サービスで特定技能外国人の雇用についてもマイナビグローバルへご相談ください!
特定技能「介護」の特徴
特定技能「介護」の在留資格の特徴としては、以下の点が挙げられます。
- 訪問介護などの訪問系サービスへの従事が可能(2025年4月~)
- 1人で夜勤が可能
- 配属後すぐに人員配置基準に加えることができる
- 特定技能外国人を支援する義務がある
- 雇用形態は直接雇用のみ(派遣不可)
- 業務範囲は介護職および看護助手などで、日本人と同様に働くことが可能
詳しく見ていきましょう。
特定技能「介護」は1人で夜勤が可能
制度上、最初から1人体制での夜勤が可能です。日本人と同じような勤務形態で働いてもらうことができます。
技能実習の場合は、2年目以降で技能実習生以外の介護職員と複数体制でなければ夜勤はできません。人手不足の現場にとって1年目から夜勤も任せられる点は、大きな違いです。
配属後すぐに人員配置基準に加えることができる
特定技能外国人は、施設に配属後すぐに人員配置基準に加えることができます。これも人手不足の現場にとって非常にメリットになる点です。
こちらも技能実習との比較になりますが、技能実習の場合は配属後6カ月間は人員配置基準に加えることができず、訪問系サービスに従事する際は、原則1年経過後に職員数に算入できるようになります。
特定技能外国人を支援する義務がある
介護分野だけに限らず、特定技能制度では、企業は支援計画を立て、計画に基づいた支援を特定技能外国人に対して行うことが義務付けられています。
特定技能外国人への義務的支援
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続き等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(自己都合退職以外)
- 定期的な面談・行政機関への通報
これらの義務的支援は事業所や自社で対応することが難しい場合、「登録支援機関」へ委託することが認められています。
受け入れにあたり、人材紹介サービスなどを利用される場合は、人材紹介会社が登録支援機関となっている場合もありますので、問い合わせてみるとよいでしょう。
▶マイナビグローバルは支援実績5,100名を超える登録支援機関です。お問い合わせは【コチラ】から
▼内製するか委託するか迷っているならこちら
施設や事業所の受け入れ要件
特定技能「介護」の外国人を雇用するには、施設や事業所側が満たすべき条件があります。
受け入れ条件
- 介護分野の特定技能協議会に加入する
- 従事させる業務が、身体介護(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助など)やこれに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助など)
- 受け入れる事業所が、介護などの業務を行うものである
- 受け入れ人数は事業所単位で日本人など※の常勤職員数を超えない数まで
※在留資格「介護」や永住者、日本人の配偶者で在留する外国人も含む
介護分野の協議会には、2024年6月15日以降、在留資格申請する前に加入しなければいけなくなりました。(加入済の場合は追加加入は不要)。
また、2024年6月15日以降は、協議会には在留資格申請する前に加入しなければなりません。
特定技能「介護」で受け入れ対象となる施設は複数ありますが、例として老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業を見てみましょう。
1.児童福祉法関係の施設・事業
2.障害者総合支援法関係の施設・事業
3.老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
4.生活保護法関係の施設
5.その他の社会福祉施設等
6.病院または診療所

対象施設詳細は以下のURLからご確認いただけます。
▶対象施設|厚生労働省
特定技能「介護」の申請要件
ここからは、外国籍の方が特定技能「介護」を取得するための申請要件について解説します。
特定技能「介護」を取得する方法は主に4ルートあります。
1つは「介護分野の特定技能1号評価試験に合格する」、2つ目は「介護分野の技能実習2号から移行する」、3つ目は「介護福祉士養成施設を修了する」、4つ目は「EPA介護福祉士候補者として在留期間満了(4年間)」というものです。
それぞれ見ていきましょう。
①介護の技能評価試験と日本語試験に合格
特定技能「介護」の在留資格を取得するための試験は、介護業務に関する「介護技能評価試験」と、日本語力を測る「日本語試験」、「介護日本語評価試験」があります。
実技試験はありません。
- 以下の試験に合格する
- 介護技能評価試験
- 日本語試験:日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)200点以上
- 介護日本語評価試験
日本語試験は、「日本語能力試験(JLPT)」N4以上、または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」で200点以上を取ることに加え、「介護日本語評価試験」に合格することも必要です。
「介護日本語評価試験」介護に関連する日本語能力を測る試験です。CBT方式で行われ、指示文は現地語、問題文は日本語です。試験水準としては、介護の声掛けや文書など、介護業務に従事するにあたって支障のないレベルの日本語が設定されています。
▶ 特定技能「介護」の試験サンプルを紹介
▶ 特定技能の試験とは?受験資格や特定技能1号の取得要件を詳しく解説
②介護分野の技能実習2号から移行する
外国人材が特定技能「介護」を取得するための2つ目の方法は、「介護分野の技能実習2号から在留資格を移行する」というものです。
以下の条件で移行をすることができます。
- 技能実習から特定技能へ移行する際の条件
- 技能実習2号を良好に修了、または3号の実習計画を修了していること
- 技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められること
もともと技能実習には介護分野はありませんでしたが、2017年に創設されました。2023年あたりから移行者が出てきています。
上記の条件を満たしている場合、技能実習生は試験を受けることなく特定技能へ移行することができます。しかし、介護分野で注意しなければならない点は、「介護日本語評価試験」は免除されないことです。必ず受験して合格しましょう。
そのほかの技能実習から特定技能への在留資格変更方法で注意すべき点は、以下の記事で解説しています。ぜひ参考にご覧ください。
③介護福祉士養成施設を修了する
介護福祉士養成課程を修了している場合は、特定技能の試験を受験しなくても、特定技能「介護」を取得できます。
介護福祉士養成課程において、介護分野における一定の専門性と技術、知識を持っていることや、日本語能力をすでに備えているとみなされるためです。
④EPA介護福祉士候補者として在留期間を満了(4年間)
EPA介護福祉候補者は、4年間、EPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事していれば、介護技術も日本語能力も十分に持っているとみなし、特定技能の試験が免除されます。
このように、特定技能「介護」分野においては在留資格の取得方法が複数あります。ほかの分野にはない特徴であり、さまざまな経歴から在留資格を取得することができます。
インドネシア国籍の在留者が急増、介護分野でも活躍
特定技能で在留する外国人の国籍は多岐に及びますが、昨今はインドネシア人材が急増しています。2025年6月末時点ではベトナムについで2番目に多い在留者数です。
なかでも介護分野での伸びが大きいのが特徴です。インドネシアでは技能実習制度の利用が盛んで、技能実習を修了した方による特定技能への移行が多いだけでなく、インドネシア国内での試験実施回数も多いことが在留人数の増加を後押ししています。
▼在留者数の移り変わりや今後の展望を解説しました!
▼現地在住のインドネシア人材はどんな人?
▼特定技能インドネシア人採用の流れを解説します!
特定技能「介護」の注意点
特定技能「介護」の外国人を採用するにあたって、注意すべき点について詳しく見ていきましょう。
事業所の受け入れ人数に上限がある
特定技能「介護」の外国人は、事業所単位で日本人の常勤職員数よりも多く受け入れることはできないと定められています。この受け入れ人数のカウントには特定技能だけでなく、在留資格「介護」や永住者、日本人の配偶者で在留する外国人も含む点に注意が必要です。
▶参考:介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針|厚生労働省
転職が可能
特定技能制度では、転職制限はありません。在留資格で認められている分野・範囲内であれば自由に転職できます。
例えば、特定技能「介護」分野の仕事から、特定技能「外食」分野の仕事に転職することはできませんが、同じ介護職や看護助手であれば可能です。
別の分野の業務を行いたい場合は、先述の通り、各分野の試験に合格する必要があります。
技能実習制度では転籍が認められていませんが、在留資格を技能実習から特定技能へ移行するタイミングで、別の企業へ転職することは可能です。ちなみに、技能実習に代わって新設される育成就労制度では条件付きで転籍が可能となることが決定しています。
▼特定技能の転職については以下の記事で詳しく解説しています。
介護分野に特定技能2号はない
特定技能には1号と2号があり、2023年からは介護を除く11分野が2号の対象となりました。
介護分野は、既存の在留資格「介護」で長期間の在留・就労が可能なため、特定技能2号の対象分野ではありません。
そのため、介護分野の特定技能1号の外国人がさらにキャリアアップを目指す場合は、介護福祉士および在留資格「介護」を目指すことになります。
介護業務が可能な他の在留資格
外国人を介護職員として雇用したい場合、特定技能「介護」を含めて4つの在留資格が存在します。ここでは、それぞれの在留資格の特徴をまとめました。
技能実習 ※廃止決定(2027年4月より育成就労が創設予定)
技能実習「介護」は日本から相手国への技能移転(国際貢献)を目的としており、学歴・資格などの要件は基本的にありません。
1年目は「技能実習1号」、2~3年目は「技能実習2号」、4~5年目は「技能実習3号」となっており、合計で最長5年の滞在が可能です。
技能実習「介護」の外国人は、母数が増えてきたので、成熟してきた制度と言えます。ただし、知識や日本語能力がほぼ無い状態から育成するので、介護業務をスムーズにできるようになるまでに時間がかかります。また、問題点が昨今指摘されたことで技能実習は廃止され、代わりに2027年4月に育成就労制度が施行されることが決まっています。
在留資格「介護」
在留資格「介護」は、介護福祉士養成学校を卒業し、「介護福祉士」の国家試験に合格することが条件の在留資格です。
在留期間の上限は設定されておらず、更新する限り永続的に日本で働ける資格です。業務制限もありません。
ただし、国家試験合格者しか取得できない資格であり、合格するには高い日本語力が必要です。そのため、該当者が少なく、採用は難しい傾向にあります。採用企業が介護福祉士養成学校の費用も出すケースが多く、その場合は費用も数百万円かかります。
特定活動EPA
EPA(Economic Partnership Agreement:経済連携協定)に基づく特定活動の在留資格です。送り出し国はインドネシア、フィリピン、ベトナムに限定されています。
この制度は、国家間の経済的な連携強化と、「介護福祉士」の国家資格取得を目的とした制度のため、一定の期間内に資格を取得できないと帰国しなければなりません。資格取得後は制限なく在留期間を更新できるため、永続的に働くことができます。
従事できる業務としては「介護保険3施設、認知症グループホーム、特定施設、通所介護、通所リハ、認知症デイ、ショートステイ」となります。
母国で看護の経験があるなど、優秀な人材も多いですが、母数が少なく対象施設による人数確保の競争が起きています。
4つの在留資格のメリット・デメリットを表で解説
ご紹介した4つの制度の違いと、メリットとデメリットを比較します。
| 特定技能「介護」 | 在留資格「介護」 | EPA | 技能実習 | |
|---|---|---|---|---|
| 業務の制限 | 制限あり | 制限なし | 制限あり (介護福祉士の資格を取得すれば一部訪問系サービスが従事可能) | 制限あり (訪問系サービス不可) |
| 在留期間 | 上限5年 | 制限なし | 原則4年 「介護福祉士」の資格取得後は制限なし | 技能実習1~3号あわせて最長5年 |
| 日本語能力 | 入国前の試験で、技能及び日本語能力(N4以上)を確認 | 介護福祉士養成校の入学者選抜の時点で、 N2を要件としているところが多い | インドネシア・フィリピン……N5 ベトナム……N3 | 入国時N4、2号に移行時にN3 |
| 母国での 能力や学歴 | 個人による。要件はなし。 ただ、上記試験に合格するか、 技能実習からの移行の場合は2年以上の実務経験がある。 | 個人による。要件はなし。 | 母国で看護系学校を卒業しているか、 介護士として認定されている。 | 監理団体の選考基準による。 |
| メリット | 実務経験か、試験合格が要件になっているので、 基礎的な介護の知識を持っていると言える。 現場に出るまでの講習機関が数時間程度でかなり短い。 定期報告は3カ月に1回、定期面談を行う。 報告の負担が少ない。 | 外国人の日本語能力が高い場合が多い。 介護の専門知識を持っている。 | 母国での学歴などが要件になっており、 人材の質が一定している。 制度の目的が介護福祉士の育成なので、 国からの支援もある。 | 国内の監理団体が研修などを行ってくれる。 |
| デメリット | 外国人支援を内製化できない場合、 登録支援団体に支払う料金が毎月発生する。 | 受け入れ調整機関がないので、 介護施設が自主的に採用活動をしなければならない。 | 採用が決まってから介護の現場に出るまでの講習が1年程度と長い。 また、介護福祉士の資格取得のためには実務者研修450時間が必要。 | 訪問系のサービスを行うことができない。 配属後6カ月間は人員配置に含められない。 資格や経験は要件になっていないので、 介護の現場に出るまでに3カ月程度の講習が必要。 技能実習状況は日誌に毎日記録。 監査報告書は3カ月に1回、 事業報告書、実施報告書は年に1回。 |
特定技能「介護」の採用はワンストップで対応できるマイナビグローバルにお任せを。資料請求はこちらから。
まとめ
日本における人手不足の加速とともに需要が高まり、多くの特定技能外国人が日本で働くようになりました。そのなかでも介護分野の在留者数の増加は著しく、在留資格取得のハードルが比較的低いことや、他の在留資格と比較して人数を確保しやすく、制度的に利用しやすいことが増加を後押ししています。今後もこの傾向は続く見込みです。
特定技能「介護」以外でも介護職に就くことはできますが、採用の難易度や受け入れ後の業務範囲などを考慮すると、特定技能「介護」が一番受け入れやすく現場で即戦力として活躍してもらいやすい在留資格と言えるでしょう。
ぜひ特定技能外国人の受け入れを検討してみてはいかがでしょうか。
【 介護施設で活躍中の特定技能の方にインタビューしました 】