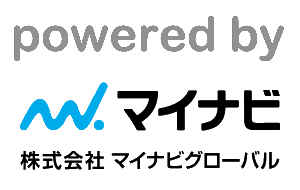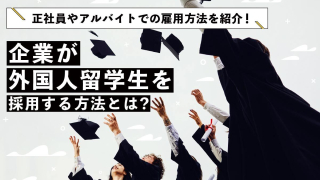特定技能1号試験とは?取得要件や詳細をサンプル付きでわかりやすく解説

今回は、在留資格「特定技能1号」の試験制度や内容、試験合格者の知識レベル、実態について説明します。
特定技能の取得要件を満たすにはどの程度の能力が必要なのか、特定技能外国人がどのようなスキルを持った人材なのかは、「どのような試験に合格したのか」というところから見えてくるでしょう。
「採用後、業務をどのレベルから教えるべきなのか」、「日本語はどの程度通じそうなのか」などの、だいたいの目安を知ることもできます。
ぜひ、特定技能人材の採用の参考にしてみてください。
目次
閉じる
在留資格「特定技能1号」とは
そもそもですが、特定技能とは、2019年4月に創設された、人手不足が深刻とされる特定産業分野(12分野)において、即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格です。
労働力を確保することを目的に創設されているため、就労ビザの代表格「技術・人文知識・国際業務」などでは行えない単純労働を付随的に可能としたことで、幅広い業務を行うことが可能です。また、技能実習2号から特定技能1号への移行も可能で、実習を終えた技能実習生が帰国せずに働き続けることができます。
対象の12分野は、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業です。今後更に、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業でも受け入れを開始し、全16分野になる予定です。
▼特定技能制度全般について詳しく知りたい場合は、下記の記事をご覧ください。
特定技能1号の取得要件
特定技能1号を取得するには、指定された以下の試験に合格するか、技能実習から在留資格変更をする2つの方法があります。
【特定技能1号取得の要件】
- ① 試験に合格する
- 各分野の技能評価試験に合格する
- 日本語試験に合格する(日本語能力試験N4以上またはJFT-basic A2相当)
- ② 技能実習2号を良好に修了し、在留資格変更で特定技能へ移行する
- 移行先の分野が実習した区分と違う場合は移行先分野の技能評価試験に合格する必要がある
即戦力として一定の業務をこなせる人材が取得できる在留資格であるため、試験では、業務に関連した技能と、業務遂行可能な日本語スキルを持っている人材かどうかが測られます。上記の要件を満たしていても、在留資格の申請・変更手続きを行う際に、別途、入管で審査が行われます。
▼技能実習から特定技能への移行に関しては、以下の記事で詳しく知ることができます。
ここからは、要件となる試験について詳しく見ていきましょう。
技能評価試験について
技能評価試験とは、対象となる各分野で外国人が即戦力(特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準)として業務を行うために必要な知識や経験を持っているかを測る試験です。そのため、技能評価試験は分野ごとに試験が分かれています。
言語・実施方法
【言語】
試験の問題文は日本語以外に、外国語で受験できるものもあります。対象言語は分野ごと異なります。日本語にはルビが振られます。
【実施方法】
技能試験は、コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式またはペーパーテスト方式等で行われます。CBT方式とはパソコンなどで受験する試験の方式のことです。CBTかペーパーテストかは分野によって異なり、試験実施機関が定める方法によって実施されます。
▶参考:試験関係|出入国在留管理庁
技能試験の受験資格
技能試験は日本国内だけでなく海外でも行われています。
● 17歳以上(インドネシア国籍の方は18歳以上)
● 在留資格を有している外国人であること ※短期滞在の在留資格でも受験可
日本国内での試験の受験資格が認められない方
(1)中長期在留者でなく、かつ、過去に日本に中長期在留者として在留した経験がない方
▶引用:試験関係|出入国在留管理庁
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等、当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方
介護分野は受験後45日間は次の試験を受けることができないため、不合格などで再受験する際には注意が必要です。
●現地の関連法令および規則を遵守し、実施するため、国によって条件が異なる
【分野別】技能試験の詳細と実施団体
特定技能は分野ごとに取りまとめる省庁が異なります。そのため、技能試験の実施団体もさまざまで、直接所管省が実施する試験もあれば、民間機関が委託を受けて実施する試験もあり、一か所に情報がまとまっていません。また、試験内容や実施状況も分野ごとに異なります。
国内試験はほとんどの分野で実施していますが、頻度が少ない分野や、コロナ禍では未実施の分野もありました。海外では「特定技能に関する二国間の協力覚書」を取り交わしている国を中心に試験が実施されていますが、未実施の国もあります。
技能試験の実施状況や合格者の数を確認すると、どの分野に人材が多くいるのか、試験を積極的に実施して合格しているのかなどの傾向を見ることができます。毎月試験を実施し、多くの合格者を出している分野は、多くの人材が求職活動を行っている可能性が高いでしょう。特に海外現地から採用する場合はこの点が重要になります。
試験を実施していない場合は、採用を希望しても人材が採用市場にいない可能性が高いということです。
このように、自社で求めている分野の採用確度や傾向を知るためにも、試験の実施状況は定期的に確認することをおすすめします。
以下に所管省庁と技能試験実施団体一覧表をまとめました。
それぞれのサイトから試験申し込みや合格者発表(実施状況)などに遷移できますので、参考にご覧ください。
| 産業分野 | 所管省 | 技能試験実施団体 |
| 介護 | 厚生労働省 | 厚生労働省 |
| ビルクリーニング | 厚生労働省 | 全国ビルメンテナンス協会 |
| 工場製品製造業(素形材・ 産業機械製造 ・電気・電子情報関連産業) | 経済産業省 | 経済産業省 |
| 建設 | 国土交通省 | 建設技能人材機構 |
| 造船・ 舶用工業 | 国土交通省 | 日本海事協会 |
| 自動車整備 | 国土交通省 | 日本自動車整備振興会連合会 |
| 航空 | 国土交通省 | 日本航空技術協会 |
| 宿泊 | 国土交通省 | 宿泊業技能試験センター |
| 農業 | 農林水産省 | 全国農業会議所 |
| 漁業 | 農林水産省 | 大日本水産会 |
| 飲食料品製造業 、 外食業 | 農林水産省 | 外国人食品産業技能評価機構 |
技能試験で出題される問題の例
例として、介護分野と宿泊分野の特定技能1号試験のサンプル問題を見てみましょう。
試験サンプル[介護]
介護技能評価試験では、介護の現場で必要な知識が出題されます。
厚生労働省の資料によると、介護技能評価試験のレベルは「介護職種の第2号技能実習修了(3年間)相当の水準である介護技能実習評価試験と同等の水準」とされています。これは、「介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベル」です。
この試験に合格すれば、3年間の技能実習を終えた人と同じくらいのことがわかっている、ということです。
例題1自己決定を支援する上で把握すべき内容として、適切なものを1つ選びなさい。
1家族の意向
2介護を必要とする人の希望
3医師の判断
4経済状況(正答:2)
出典:厚生労働省|介護技能評価試験サンプル問題
試験内容は下記の表のとおりです。合格基準は総得点の60%以上です。
| 介護技能評価試験 | 介護日本語評価試験 | |
| 問題数・試験時間・試験科目 | 全45問 60分 ►出題基準 <学科試験:40問> ・介護の基本(10問) ・こころとからだのしくみ(6問) ・コミュニケーション技術(4問) ・生活支援技術(20問) <実技試験:5問> ・判断等試験等の形式による実技試験課題を出題 | 全15問 30分 ・介護のことば(5問) ・介護の会話・声かけ(5問) ・介護の文書(5問) |
試験サンプル[宿泊]
特定技能「宿泊」の試験は、宿泊業で働くために必要な知識を「フロント業務」「広報・企画業務」「接客業務」「レストランサービス業務」「安全衛生その他基礎知識」の5つの分野から出題される問題により確認します。学科試験と実技試験があり、学科試験は〇か×で答えます。
以下、試験のサンプル問題です。
【学科試験】
●「ホテルのチェックインとチェックアウトの時間は法律で定められている」(×)
●「ホテルを宣伝するためにホテルで撮影した写真であれば、お客様が映り込んでいても、誰にも許可を得ずに使用することができる」(×)
●「メニューの注文を受けるときは、お客様に食物アレルギーがあるかどうかを確認する」(〇)
出典:一般社団法人 宿泊業技能試験センター
【実技試験】
● 受験者の外国人はホテルの従業員になったつもりで、宿泊業の基本的な事項に関する質問に答えます。
出典:一般社団法人 宿泊業技能試験センター
業務に直結した内容が出題されます。いずれの問題も、宿泊業で働くのであれば知っておかなければならないことです。
日本語の試験について
「日本語能力試験(JLPT)」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-basic)」のどちらかに合格すれば問題ありません。
国際交流基金日本語基礎テストのほうが年間を通じて多く開催されています。在留資格を申請するタイミングにあった試験を受験することが多いでしょう。
日本語能力試験 (JLPT)
日本語能力試験(JLPT)とは、日本語を母国としない人を対象に、日本語能力を測定して認定する試験です。
試験は年2回、7月と12月に実施され、日本国内だけでなく海外でも開催されています。
試験内容は日本語でコミュニケーション上の課題を遂行する能力を測るための質問で構成されています。問題文の言語は日本語のみで、会話や作文の試験はありません。試験はマークシート方式で、N1からN5まで5段階にレベルが分かれており、特定技能で要求されるのはN4以上です。N4とは、基本的な日本語を理解することができるレベルとされています。
【N4】 基本的な日本語を理解することができる
読む
● 基本的な語彙や漢字を使って書かかれた日常生活の中でも、身近な話題の文章を、読んで理解することができる。聞く
▶引用:日本語能力試験|国際交流基金 日本国際教育支援協会
● 日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる。
▼日本語能力試験へはこちらから申し込めます。
日本語能力試験|日本国際教育支援協会
▼日本語能力試験合格者ってどれくらい話せるの?と思ったら以下をご覧ください。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-basic)
国際交流基金日本語基礎テストとは、主に就労のために来日する外国人が遭遇する生活場面での必要なコミュニケーション能力を測定する日本語試験です。試験は国内外で実施されています。日本語能力試験(JLPT)のようなレベル区分はなく、受験レベルは1つのみです。
特定技能1号の取得要件を満たすためには、250点中200点以上(A2レベル)を取る必要があります。CBT(パソコンやタブレットを使用)方式で実施され、会話や作文の問題はありません。問題文は英語で書かれていますが、「Your Language」ボタンを押すと現地語で読むことができます。
▼国際交流基金日本語基礎テストにはこちらから申し込めます。
JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト|国際交流基金
特定技能を取得できる人材のレベルとは?
特定技能の試験に合格した外国人は、その業務の基本的なことを理解し、即戦力として働ける技能を持ち合わせていると言えるでしょう。これは、3年間の技能実習を良好に修了すれば試験が免除される点からもうかがえます。また、業務に必要な範囲での日本語コミュニケーションも可能です。
とはいえ、特定技能試験はあくまでもペーパーテスト(職種によっては面接試験)で、「業務の基本が理解できていることの証明」と考えると良いでしょう。
日本語能力N4レベルでは、簡単な日本語での挨拶はできますが、複雑な会話は難しいかもしれません。しかし、基本を理解している人材であれば、現場での戦力になりやすい点は大きなメリットです。元技能実習生など日本での就労経験がある人材であれば、日本文化への理解や日本語能力の高さも期待できます。
能力や条件を正しく理解したうえで、特定技能外国人の採用をぜひ検討してみてください。